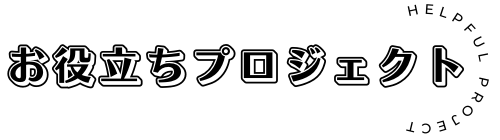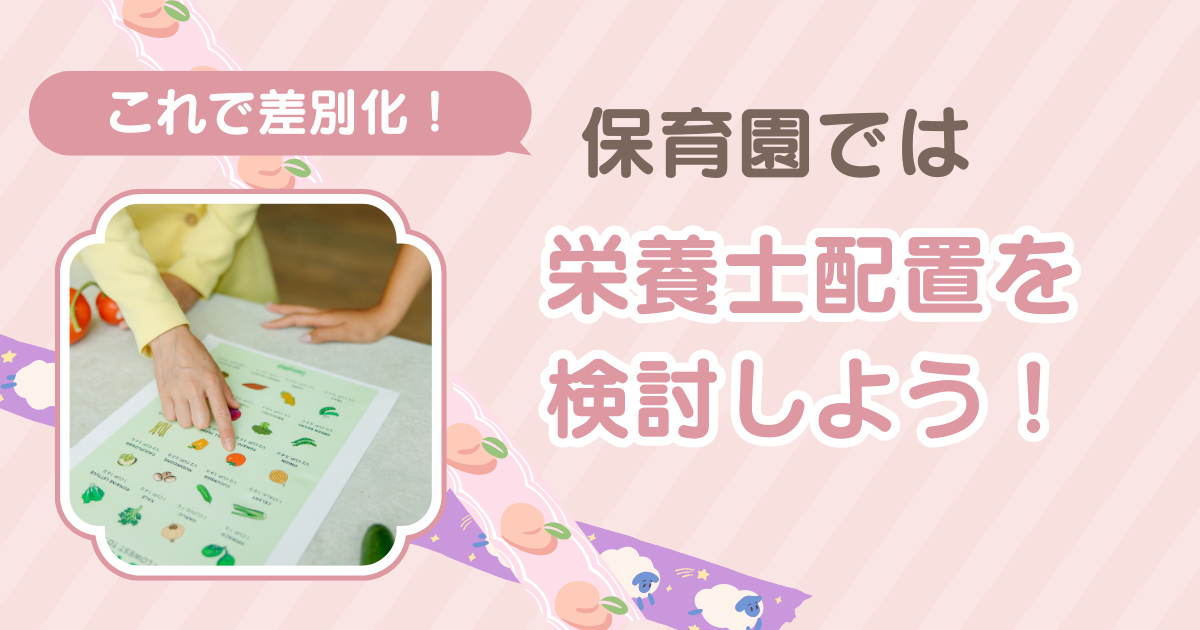問題提起:
栄養士が活躍する職場の一つに保育園がありますが、保育園で働く栄養士はどのような仕事をしているか知っていますか?安心安全な食材を使ったバランスのよい給食提供や食育の実施など、求められることはいろいろとありますが、どのような役割があり、日々どのような業務を行っているのでしょうか?そもそも、どうして保育園には栄養士が必要なのでしょうか?
この記事を読んでわかること:
この記事では、保育園に栄養士を配置することの意味や、栄養士がどのような業務を行っているのかについてを詳しく説明しています。また、保育園で栄養士として働くためにはどのようなスキルや資格がいるのか、採用すること、働くことのメリットやデメリットについても説明しています。
この記事を読むメリット:
この記事を読むことで、保育園に栄養士がいることで子どもたちにどのような効果があるのか、そのために栄養士がどのような仕事をしているのかがわかります。また、これから子どもたちと関わる中で働きたいと思っている人への参考になったり、働いている人へのフォローアップに繋がります。
なぜ保育園に栄養士は必要なのか?
保育園における栄養士の配置状況は、施設の規模や運営方針、自治体の基準によって異なります。保育園では調理員の配置は義務付けられていますが、栄養士の配置は義務ではありません。しかし、子どもたちの健康と成長を支えるために、より専門性の高い技術で栄養管理を行うため、栄養士を配置する保育園も増えてきました。
栄養士を配置するねらい
現在の保育園では子どもの減少、運営の多様化の渦中であるため、保育内容で他園との差別化をはかる必要が出てきています。今ではリトミックはもちろん、英語教育や体操教室など、各保育園は工夫を凝らした実に様々な取り組みを行う事が当たり前となってきています。そのような差別化の中でも、特に給食や食育に注目している保護者は多く、保育園はその要望に応えるため独自の献立を作って提供したり、食育を行ったりと子どもたちの状況に合わせた対応を取る必要性が高まっています。保育園としても食に対する対応は、給食という保育園運営において切っても切れない点であるため、栄養士の配置対応は受入やすく、外部の講師を招聘しての英語教育などに比べてコストや人員確保が比較的容易となるため、導入ハードルが低いというメリットがあります。
また保育園では、食物アレルギーを持つ子どもや、離乳食を食べる子どもたちの発達に合わせた食事の提供など、小さいお子さんだからこその個別対応も求められます。その際、専門的な知識を持っている栄養士を配置することで、保護者の保育園への信頼も高まり、子どもの食事についての相談やアドバイスを受けられる場となることもできるでしょう。
栄養士を配置するための課題
しかし、保育園に栄養士を配置する際にはいくつかの課題も考えられます。栄養士を雇用するには当然人件費がかかります。特に小規模な保育園では、予算の制約が大きな課題となることがあります。また、栄養士が少人数で働いている場合には、栄養士が休んだ時の対応が非常に重要な課題となります。栄養士の業務が一人に集中していると、突発的な休みの場合、他のスタッフが対応できないことがあります。普段から栄養士が業務を「一人で抱えすぎない」ことが重要です。チーム或いは外部専門家と協力し、互いにカバーし合える体制を整えておくことが必要です。
保育園栄養士の役割と仕事内容とは?
保育園栄養士は、単に食事を提供するだけでなく、子どもたちが健康に成長するためのサポートを行い、食を通じた豊かな経験を提供する役割を担っています。その役割を果たすためにどのような業務を行っているのでしょうか。
献立作成
各年齢層の子どもたちに必要な栄養素を考慮し、バランスの取れた献立を作成します。旬の食材を取り入れたり、行事食の献立も作ります。また、 食物アレルギーを持つ子どもたちにも対応した安全な献立を作成します。
食品調達と在庫管理
新鮮で安全な食材を選び、適切な方法で保存・管理します。食品の購入費用を管理し、予算内で高品質な食材を調達し、先入れ先出しを徹底する、その日に必要な分だけ購入し無駄を省く等の在庫管理も行います。
調理と衛生管理
大規模園では調理スタッフが調理を担当し、栄養士は管理業務が中心となるところもありますが、栄養士が直接調理を担当するところもあります。また、調理スタッフに対して安全で美味しい食事を作るための指導を行い、調理場の清潔さを保ち、衛生基準を遵守するための指導も行います。
食育活動
子どもたちや保護者に対して、食事の重要性や栄養についての教育を行います。野菜の栽培体験やクッキング保育など、子どもたちが食に興味を持つための食育活動を企画し、実施しています。
事務作業
献立表の作成・印刷(保護者配布用など)、食数の管理・給食日誌の作成(食事内容や園児の食べた量の記録など)、衛生管理の記録(冷蔵庫の温度・食材の消費期限・調理場の清掃、調理器具の消毒の記録など)の栄養に関する書類を作成します。行政への対応として、自治体への報告書を作成したり監査対策も行っています。
健康管理
身長や体重の測定を定期的に行い、成長曲線に沿った発育を確認したり、児童が摂取する食事内容や量を記録し、バランスの取れた栄養を確保します。また、アレルギーを持つ子どもの食事を徹底的に管理し、アレルギー反応を予防します。
このように、保育園で働く栄養士は子どもたちが健康的に成長できるよう、保育士や保護者と連携を取りながら日々の業務を進めていきます。
保育園栄養士の1日の流れ(例)
それでは、保育園で働く栄養士の主な1日の流れはどのような感じなのでしょうか?保育園によって異なりますが、8:00~17:00、9:00~18:00などの8時間勤務(休憩1時間)になるところが多いです。一例を紹介します。
8:00 出勤、仕込み
9:00 朝礼(食数確認)、給食調理、検品・検収作業
11:00 盛り付け、給食提供
12:00 片付け、洗浄
13:00 休憩
14:00 おやつ調理、提供
15:00 片付け、洗浄、書類の記入
16:00 掃除、献立作成・発注等の事務作業
17:00 退勤
延長保育の子どもがいる場合は夕食を提供する保育園もあるので、栄養士の勤務時間をずらして対応しているところもあります。保育園の規模によって必要な調理人数も違うので、シフト制で勤務時間をずらして調整しているところが多いです。
保育園栄養士に必要な資格とスキルとは?
保育園で栄養士を採用する際、資格やスキル、どのような知識があるとよいのでしょうか?主に必要となるものを紹介します。
必要な資格とは?
栄養士免許が必要になります。栄養士養成施設(大学・短大・専門学校)で2年以上学び、卒業すると取得が可能です。保育園においては管理栄養士である事は必須ではありません。一方で一定の知識を証明する基準であるともいえるでしょう。
必要なスキルとは?
栄養管理の知識と献立作成スキル
幼児期に必要な栄養素を踏まえ、成長をサポートする献立を作ります。アレルギー対応食や離乳食・幼児食の知識も必要です。献立作成の経験の有無が一つの判断基準になるでしょう。
調理スキルや衛生管理の知識
保育園のポリシーにもよりますが、調理を担当することも多いです。調理が好きであったり、調理経験があると即戦力になることも可能です。また、食中毒を防ぐための衛生管理やアレルギー児への食事提供の注意点を理解しておくなど、衛生管理や食品の安全管理も求められます。
事務処理・書類作成スキル
献立作成や給食日誌、発注書などの書類を作成することも日々の業務の1つです。Excelや専用ソフトを使うことが多いので、パソコンスキルもあると便利です。また、発注作業では限られた予算内でコストを管理しながら必要な食材を適切に発注することも求められます。
コミュニケーション能力
子どもたちへ食べることの大切さを楽しく伝えたり、クッキング保育や野菜の栽培活動などを企画し、実施することもあります。また、保護者対応として栄養相談や食事指導を行うこともあるため、簡潔にわかりやすく伝える説明力が必要です。園全体で子どもを育てるためには保育士や看護師と情報共有をしっかりしていることも重要になってきます。
伝えるべき?保育園栄養士として働くメリット、デメリット
保育園栄養士として働くことには、いくつかのメリットとデメリットがあります。施設のポリシーにもよりますが、採用に際して伝えるべきかも含めてメリット・デメリットは十分理解している必要があります。
メリット
子どもの成長を支えられるやりがい
乳幼児期の食事は成長に大きく影響するため、栄養士としての知識や工夫が直接子どもの健康に貢献できます。自分の作った給食を食べる子どもたちの姿が見られるというのが一番のやりがいです。好き嫌いを乗り越えたり、食べる楽しさを伝えることもできます。また、子どもたちやその家族に喜ばれることで、社会的に貢献しているという満足感を得られます。
安定した勤務環境
保育園は通常定期的な業務時間があり、仕事のリズムが一定しています。土日祝休みのところも多いです。(土曜日勤務あり、シフト制のところもあります)。また、公立・私立共に比較的安定した職場で福利厚生もしっかりしていることが多いです。
調理のスキルが身につく
調理業務を兼任する場合、実践的な大量調理のスキルが身につきます。献立を考える際に、創造性を発揮することもできます。
デメリット
業務量が多い(幅広い業務)
献立作成、発注、調理、衛生管理、アレルギー対応、食育活動など、多岐にわたって業務を遂行する必要があります。園によっては栄養士が一人しかおらず、負担が大きいこともあります。また、調理員が不足している場合は栄養士も調理業務を多く担当することがあります。休憩時間が短い、時間外業務が発生する場合もあります。
給料が低い
保育園栄養士の需要は高いにも関わらず、一般的に他の施設で働く栄養士と比較して給料はやや低い傾向にあります。公立保育園は職務のため安定していますが、私立は園によって大きく差があることもあります。裏を返せば、この点を改善する事で多くの求職者からの応募が期待でき、採用する側に選ぶ機会が増える可能性がある事を意味しているとも言えます。
体への負担や心的ストレス
多くの時間を立ち仕事で過ごし、重い物を運ぶこともあるため、体力的に負担がかかることがあります。また、食物アレルギー対応を徹底する必要があり、間違えれば命に関わるリスクがあったり、衛生管理や食中毒予防にも細やかな注意を払わなければなりません。「子どもが家ではご飯を食べない」「好き嫌いが多い」といった相談を受けることもあり、保護者への対応に気を遣うこともあります。
保育園栄養士の仕事は、子どもたちの健康を支えるやりがいのある仕事ですが、業務の幅が広く負担が大きくなりやすい面もあります。安定した環境で働きたいのか、食育活動を重視したいのか、調理業務をどの程度するのかなど、自身の保育園が求職者の求めるものに合っているかを見極める事も、採用する側にとって重要なポイントになります。
栄養士の配置によるコスト増の回避策
前述したように、保育園にとって栄養士を配置することは差別化要因の一つとして重要なポイントとなる事はおわかりいただけたかと思います。一方で、特に小規模保育園などにおいては人員1人分の増加コストを予算として割く事が難しい施設もあるかと思います。そのような施設での対応策について考えたいと思います。
ダブルライセンス者の採用・社員の資格取得奨励
栄養士のみの仕事を行う方を採用する事が負担となるのであれば、保育士・栄養士のダブルライセンス取得者を採用するのも一つの方法になります。また栄養士の資格取得には一定の就学・実務経験等が必要となりますが、保育士の取得は四年制大学を卒業していれば原則可能です。そのため、既に栄養士の資格を持ち働いている方がいる場合は、会社として保育士資格の取得を奨励することで、ダブルライセンスの職員を増やすことも可能です。
限定的な雇用形態での採用
コスト削減の方法としては、パート社員として栄養士を採用するのも一つの方法です。制約は出てしまうものの、業務や時間を限定した働き方を希望している方も一定数いらっしゃるため、その方のニーズに沿った形でかつ、フルタイム社員に比べてコストを削減して栄養士を登用することが可能となります。
外部専門家の利用
意外と見落とされがちですが、外部専門家の利用を検討するのも有用です。業務内容はパートよりも更に限定されてしまいがちですが、専門性に関しては申し分なく、場合によってはパート社員のコストと変わらない費用で高いパフォーマンスを期待することができます。
まとめ
保育園にとって栄養士を配置することで、多様化する保育園へのニーズに対応することが可能となります。一方で、保育園は今後より一層コスト意識を持って運営をしていかなければならなくなります。そのような状況に対応するため、栄養士業務を内製化するか外部委託するかを含めて検討を行い、最適な運営方法を検討してください。この記事がその参考になれば幸いです。
弊社は保育士・栄養士の業務負担軽減を目指したBPOサービス(事務業務のサポート)を提供しています。
BPOサービスの利用により、保育園のスタッフは本来やるべき業務に、より一層貴重な時間を割く事ができるようになります。今回のような栄養士業務を自社の雇用として採用するのではなく、外部に委託することでコストの削減はもちろん、より高い専門的なサービスの提供も期待できます。
また我々はDX化にも強みを持ち、保育園の単なるシステム化ではない、仕組みづくりをお手伝いします。人材不足はもちろん、業務効率化ができない、年々コスト増に困っているなど、保育園経営にお悩みの方は是非一度、弊社にご相談下さい!